事業承継における遺留分とは?民法特例の適用条件や適用する手順を解説!
最終更新日:2024-03-30
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪う事のできない遺産の一定割合の留保分のことを指します。
遺留分に満たない遺産しか受け取れていない状況にある場合は、遺産を多くもらったほかの相続人に対して、遺留分侵害額請求と言われる遺留分との差額を金銭で支払うように請求することが可能です。
事業継承においてもこの遺留分に注意を払わないと、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまい自社株式や事業用資産の売却を迫られる場合があります。
この記事では、遺留分についての基礎知識と事業継承における注意点や遺留分に関する民法特例などについて解説していきます。
目次
事業継承での遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利です。これは偏った相続が行われて被相続人の遺族の間で不公平が生じてしまう事を防ぐためにあります。
遺留分は、このような遺族同士の公平性とその他遺族の生活を担保するために定められた制度です。仮に遺言で特定の相続人にすべてを相続させると決められていても、この遺留分と言われる部分にあたる遺産の取り分の支払いは受けられます。
また事業継承では、この遺留分がもとで問題が発生する場合があります。事業継承を行いその後の経営を安定させるためには、基本的に後継者に自社株式や事業資産などを集中して引き継ぐ必要があります。
しかしここで問題になるのが遺留分で、特定の人物のみに財産を集中させて相続を行うと、そのほかの相続人の遺留分の権利を侵害するがある事です。
後継者しか相続人がいないのであれば問題ないのですが、後継者以外に相続人がいるような場合は、この部分について注意しなければなりません。
遺留分の相続財産に対する割合
遺留分の権利を持つ人は、被相続人の配偶者と子供と直系尊属と言われる被相続人の父母と祖父母が対象です。またこの中でも、相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分と法定相続分の割合を乗じた割合で分配することになります。相続人の遺留分の相続財産に対する遺留分割合は、以下のとおりです。
(1)配偶者のみ – 2分の1
(2)子どものみ – 2分の1
(3)直系尊属のみ – 3分の1
(4)兄弟姉妹のみ – 遺留分なし
(5)配偶者と子ども – 配偶者が4分の1、子どもが4分の1
(6)配偶者と父母 – 配偶者が3分の1、父母が6分の1
(7)配偶者と兄弟姉妹 – 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
遺留分の金額は、相続財産額とた特定の相続人が生前贈与を受けて特別受益がある場合には、生前贈与された分の財産も加算して負債などを差し引いた金額を元に計算されます。
そこに遺留分の割合と法定相続分の割合を乗じる事で計算されるという事を覚えておきましょう。
遺留分の計算例
ここでは、2つのケースを遺留分の計算例として紹介します。
ケース➀
相続人:「子ども3人」
遺産総額:「2億円」
相続開始前の1年間にした生前贈与額:「3,000万円」
債務:「5,000万円」の場合
- 遺留分算定基礎財産 2億円 + 3,000万円 – 5,000万円 = 1億8,000万円
- 子ども全員の遺留分 1億8,000万円 × 1/2(遺留分割合) = 9,000万円
- 子ども1人遺留分 9,000万円 × 1/3 (法定相続分割合) = 3,000万円
このケースでは、子ども1人の遺留分は3,000万円です。
ケース➁
相続人:「配偶者1人と子ども1人」
遺産総額:「2億円」
相続開始前の1年間にした生前贈与額:「6,000万円」
債務:「2,000万円」の場合
- 遺留分算定基礎財産 2億円 + 6,000万円 – 2,000万円 = 2億4,000万円
- 配偶者と子どもの遺留分 2億4,000万円 × 1/2(遺留分割合) = 1億2,000万円
- 配偶者の遺留分 1億2,000万円 × 1/2 (法定相続分割合) = 6,000万円
- 子どもの遺留分 1億2,000万円 × 1/2 (法定相続分割合) = 6,000万円
このケースでは、配偶者の遺留分は6,000万円で子どもの遺留分も6,000万円です。
このように計算することで、それぞれの遺留分を求める事ができます。
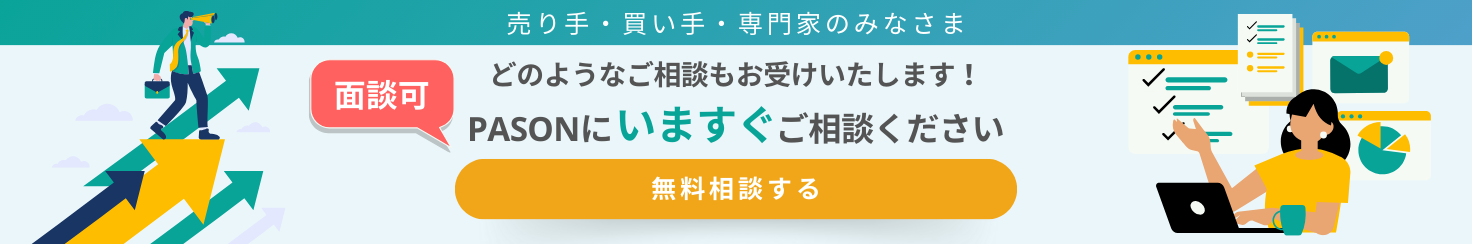
遺留分が認められない場合
遺留分の請求権を持った相続人でも、場合によっては遺留分が認められないこともあります。
相続欠格者
故意に相続人が被相続人を殺害したり、または詐欺や脅迫を利用して遺言を取り消しや変更させたり、遺言書の偽造や隠蔽などを行うと相続人の資格を失います。
相続廃除を受けた人
被相続人が、一定の事由(非行や虐待など)が存在する推定相続人に相続させたくない場合は、家庭裁判所に排除の審判を請求します。この排除の審判が確定すると、推定相続人は、相続権を失います。相続排除された人には、法定相続分も遺留分も認められません。
またこの相続の廃除を申し立てできるのは、被相続人だけです。またこの申し立てができるのは、被相続人のみです。
相続放棄した人
自分の意思によって相続を放棄した人は、相続人ではないとみなされます。そのため遺留分と法定相続分は認められません。
遺留分を放棄した人
遺留分の権利を有する人でも、家庭裁判所からの認可を受けた場合遺留分の権利を放棄できます。遺留分を放棄した場合は、その人の遺留分は認められません。
事業承継における遺留分の注意点
ここまでは一般的な留意分について解説してきましたが、ここでは事業継承で留意分が問題になるような場合を解説していきます。
遺留分侵害してしまう可能性がある
遺留分侵害とは、被相続人が財産を生前贈与や遺言などで遺留分に相当する財産を受け取れない状態を指します。
例を挙げると、先代の経営者である父と母、後継者である子供の家族構成では「母の遺留分は1/4」「子供の遺留分は1/4」の遺留分が権利として保障されています。
しかし、先代の経営者である父から後継者である子供に自社の株式や事業用資産などを全て継承した場合、母は遺留分に当たる財産を受け取ることができません。
しかし事業継承では後継者に集中して株式や事業用資産などを継承する事がありますが、推定相続人が1人ではなく複数存在するような場合では、ほかの人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分侵害額請求を受けるリスクがある
遺留分侵害額請求と呼ばれる遺留分を侵害された相続人が裁判所を通して遺留分侵害額に相当する金額を請求するものです。仮に後継者がほかの相続人によって遺留分侵害額請求を受けてしまった場合、遺留分侵害額に当たる金額の支払いを行うための資金が必要です。
しかし支払う資金が足りないと株式や事業用資産の売却を迫られる可能性があります。このような株式や事業用資産の売却は、今後のスムーズな事業継承に悪影響を及ぼします。
そのため事業継承する際には事前に留意分について対策を検討すると良いでしょう。
遺留分の事前放棄は手続きが大変
遺留分の事前放棄という制度を利用して遺留分によって発生しうるトラブルを避けられます。この遺留分の事前放棄は、被相続人がまだ生きている間に相続人が遺留分を放棄することを指します。
これが事業継承における遺留分のトラブルを避ける方法です。また遺留分を事前放棄する際には相続人がそれぞれ家庭裁判所に申し立てを行い許可を受ける必要があります。
しかし一定の要件を満たさなければいけないため、遺留分の事前放棄を活用する場合は、相続人の手続きの負担が大きい部分にも気を付ける必要があります。また遺留分放棄の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 家事審判申立書
- 現金・預貯金・株式などの財産目録
- 不動産の目録
- 被相続人予定者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
上記の書類が必要となります。
遺留分に関する民法特例について
事業継承を円滑に進めるために、経営承継円滑化法で遺留分に関する民法の特例が定められています。
この民法特例を活用すれば、会社や個人事業の経営を継承する際に、除外合意や固定合意といった法的手段を取る事ができます。
これは、先代経営者から後継者に贈与された自社株式や事業資産の価格について除外や固定を行うものです。しかし、これには推定相続人の全員が合意する必要があります。
除外合意
除外合意とは、株式や事業用資産などについて留意分の対象から除外する合意です。これを行うことで、その財産については遺留分の対象ではなくなるため、遺贈や贈与をしたとしても遺留分侵害額請求は起こりません。そのため安心して事業用資産や自社株式を集中して継承できます。
固定合意
固定合意は、遺留分侵害額を行う場合の財産評価額を固定する合意です。遺留分侵害請求が起きてしまうと、対象になる資産を評価後にその分のお金を支払う必要があります。しかし評価額が想定を超えるような高額になってしまった場合、後継者にとってとても大きな負担になってしまいます。
そのためこの合意により、遺留分算定の基礎となる評価額を贈与時に固定することで、これから起こりうる遺留分侵害額請求に備えられます。また固定合意が可能なのは自社株のみです。

遺留分に関する民法特例を適用できる要件
事業継承における遺留分に関する民法特例の適用を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。また会社の場合と個人事業主の場合で変わるためそれぞれ解説します。
個人事業主の場合
- 先代経営者の場合
- 合意時点に3年以上継続して事業を行っている個人事業主であること
- 後継者に事業用資産をすべて後継者に贈与していること
- 後継者の場合
- 合意時点において個人事業者であること
- 中小企業者であること
- 先代経営者からの贈与等により事業用資産を取得したこと
個人事業主の場合は、上記の条件を全て満たす必要があります。
会社の場合
- 会社
- 中小企業であること
- 意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
- 先代経営者
- 過去または合意時点において会社の代表者であること
- 後継者
- 合意時点において会社の代表者であること
- 先代経営者からの株式の贈与を受けていること
- 会社の議決権の過半数を保有していること(推定相続人以外の方も対象)
会社の場合は、上記の条件を全て満たす必要があります。
事業承継における遺留分に関する民法特例を適用するプロセス
遺留分に関する民法の特例の適用を受けるためのプロセスは主に以下の流れになります。
- 事業用資産や自社株式などの生前贈与
- 推定相続人全員と後継者の合意を得る
- 経済産業大臣に申請書を提出し確認を受ける(個人事業者の場合は認定支援機関の確認が必要)
- 家庭裁判所から許可を得る
それぞれの手続きについて解説していきます。
推定相続人全員と後継者の合意を得る
まず先代経営者の推定相続人全員で合意書を作成します。ここでいう推定相続人全員とは、遺留分の権利を持っている人物に限定されます。また合意書には特定のフォーマットは存在しませんが、以下の内容が記載されます。
- 会社の経営承継の円滑化のために合意すること
- 後継者が先代経営者から贈与された自社株式は遺留分の計算から除外する
(もしくは遺留分の計算に算入する金額を固定する)
- 後継者以外の推定相続人がとることができる措置
- 衡平を図るための措置
上記のような内容が記載される事が一般的です。
経済産業大臣に申請書を提出
合意後1ヶ月以内に後継者は遺留分に関する民法の特例にかかる確認申請書と必要書類を経済産業大臣に提出する必要があります。また主な必要書類は以下の通りです。
- 定款と株主名簿の写し
- 登記事項証明書
- 貸借対照表と損益計算書
- 上場会社でない旨の誓約書
- 従業員数証明書
- 現在の経営者と推定相続人全員と後継者の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 税理士などの証明書
税理士などの証明書については、固定合意の場合に必要となります。
家庭裁判所から許可を得る
経済産業大臣から確認書の交付を受けてから、確認された日から1ヶ月以内に家庭裁判所へ申立書を提出して、許可を得ます。ここでは主に、推定相続人と後継者が同意しているのかを判断されます。
遺留分に関する民法の特例が適用できない場合
これまで解説してきたように、特例の適用を受けるには、推定相続人と後継者の全員が合意する必要があります。
なんらかの理由により1人でも合意しないような場合では、特例を適用できません。このような場合に考えられる別の対処法がいくつかあるため解説していきます。
自社株の評価額を引き下げて後に贈与を実施する
先代経営者と後継者の関係に問題が無ければ、何らかの方法によって自社株の評価額を引き下げた後に生前贈与を行う方法です。
この方法のメリットは、自社株の評価を引き下げた後の評価額の為税負担が軽くなります。また非上場企業の自社株の評価は比較的操作が容易な点もメリットです。
また先代経営者と後継者の関係が円滑な場合は、後継者に自社株を贈与した後でも先代経営者が実質的に経営権を維持し続けることが可能です。
遺留分に配慮した遺言書の作成
相続の際に遺言書がある場合は、遺言書の内容通りに手続きを進めるのが原則です。
しかし遺言書に記載されている内容が遺留分を侵害している場合は、相続人によって遺留分侵害額請求権を行使できます。
この方法は、相続トラブルを避けるために遺言書を作成します。そのため遺留分侵害額請求権を行使されてしまっては意味がありません。
したがって遺言書を作成する場合は、相続人の遺留分に配慮する事が大切です。
生命保険の受取人を後継者にしてかける
遺留分侵害額請求権が行使される可能性がある場合は、受取人を後継者にした生命保険をかける方法です。
生命保険金は遺産分割協議の対象とならないため、遺留分の支払いに使用できる現金を残す事ができます。
具体的には、生命保険の受取人を後継者にしておいて、自社株を後継者に相続させ、遺留分侵害額請求権を行使されたら保険金を使い遺留分を支払います。
こうする事で、自社株を後継者に引き継いだ上で遺留分トラブルを避ける事ができるでしょう。

まとめ│遺留分に関する民法特例を活用して相続トラブルを避ける
この記事では、主に事業承継における遺留分について解説してきました。後継者に事業承継をする場合、自社株式や事業資産などを後継者に集中して引き継ぐ必要があります。
しかしほかの相続人の遺留分を侵害してしまい、後から遺留分の金銭を要求されて事業資産や自社株を手放してしまう事になってしまっては、円滑な事業運営に支障が出てしまいます。
そのため事業承継における遺留分に関する民法特例の適用を検討したり、それが無理な場合でも自社株の評価額を引き下げてから贈与を行ったり、生命保険の受取人を後継者にするこ
とで対策する事ができます。後継者に事業承継を考えている場合は、遺留分について留意しておく必要があるでしょう。
またPASONでは、M&Aのマッチングやサポートを行っております。PASONの魅力は、業界最低水準の料金で「売り手側」「買い手側」どちらのお客様にも、満足いただけるサービスを提供しています。また全案件の財務情報が検証済みのため、安心して交渉いただけます。
売り手側の企業様は無料でご利用いただけますので、事業承継やM&Aを検討しているが疑問や悩みがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。







